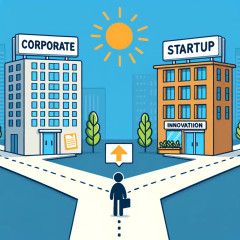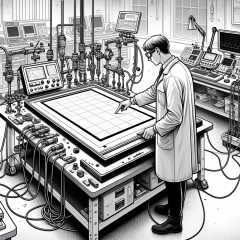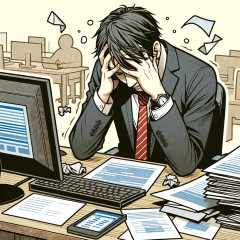日々の気づき/ブログ
考え過ぎる人が直面する新規事業創出の課題:分析麻痺を乗り越えて成功へ導く戦略
MBAを保有する人や企業の企画部にいる人たちは、幅広い知識と戦略的思考力を兼ね備えています。しかし、新規事業を立ち上げる過程では、予期せぬ困難に直面することがしばしばあります。これは、理論的な知識だけでは現実のビジネス課題に対応するには不十分であるということを示唆しています。
「分析麻痺」という現象が、その主な原因の一つです。過度な分析と計画によって、実行に移るタイミングが遅れるのです。彼らはビジネスモデルの策定、市場分析、リスク評価などに優れた能力を持っていますが、時にこれが行動を妨げる原因となることがあります。市場の実在性や利益の可能性、製品の製造可能性に関する深い調査と分析を行う傾向があるのです。
このような状況で、完璧主義に陥りやすいのですが、ビジネスの世界では不確実性と向き合い、時には直感に基づいて決断を下すことが重要です。新規事業は、市場との対話を通じて形成されるものであり、柔軟に、迅速に方向転換を行う能力が求められます。
新規事業を推進する際には、理論的な思考が重視されるものの、現実はしばしば予測不可能です。
結論として、新規事業を成功させるためには、理論的な知識と実践的な行動の適切なバランスが必要です。過度な思考に囚われず、実行に移す勇気が重要。市場の反応を得て、失敗から学びながら修正を加えていくことが、成功への道です。「Just Do It」という言葉に象徴されるように、ある程度の思考の後には、積極的に行動に移すことが求められます。これにより、新規事業の第一歩が踏み出されるでしょう。
新規事業の舵取り:大企業の慎重なアプローチとベンチャーの柔軟性 - 専門コンサルタントによる成功へのナビゲーション
大手企業は新規事業の推進に際し、市場調査や競合分析を徹底的に実施します。市場が小さく、十分な利益が見込めないと判断された場合、計画段階で事業を中止することが一般的です。これはリスク回避と既存事業への集中を優先する大企業の戦略に起因します。
対照的に、ベンチャー企業は新規事業を立ち上げる際、徹底した市場調査や競合分析よりも、実際に事業を開始して市場の反応を見てから改善していく手法を採ります。市場規模が小さくても、生存戦略として他のアプローチを模索し、差別化を図ります。このプロセスは、体操の三回転半ひねりのように、初期計画が進行中に変化する過程です。結果として、計画とは異なる商品化がなされ、市場で成功をおさめることもありますが、当然ながら生き残れないベンチャーも少なくありません。ベンチャー企業はリスクを恐れずに新しい挑戦を重視し、生き残りを目指します。
新規事業のアプローチは企業によって異なりますが、成功の鍵は市場の変化に対する柔軟性と進化の能力にあると言えます。リスク回避に注力するあまり新規事業の機会を逃すことがある大企業は、新たな事業を創出するためには既存のアプローチや評価基準を見直す必要があります。
一方で、ベンチャー企業は積極的な行動を通じて市場での生存と成長の機会を掴みます。成功するためには、変化に適応し、進化する柔軟さが必要です。体操の三回転半ひねりのような迅速で柔軟な対応が求められます。
新規事業の構想にあたり、考え過ぎて行動に移せないでいる場合は、少しでも前進して市場の声を聞くことが重要です。
『経験豊富なコンサルタント』が背中を押すサポートを提供します。お気軽にご相談ください。私のような外部の専門家が上司への説得材料としてもお使いいただけます。
市場変化と企業内課題: 大企業が直面した技術開発プロジェクト失敗の教訓2
若かりし頃、私が関わったタッチパネルの開発プロジェクトは、研究開発の領域での挑戦の一例と言えます。このプロジェクトは、新しい技術の市場導入に際し、技術の優位性だけではなく、市場のニーズとタイミングの理解がいかに重要であるかを教えてくれました。
市場ニーズとタイミングの見極め
2000年頃に始まったこのプロジェクトでは、独自のタッチパネル技術をベースにした製品の開発を試みました。技術的には順調に進展し、やがてプロトタイプが完成しました。しかしながら、市場の動向を見極めきれず、最終的にプロジェクトは中止という形になりました。確かに、その当時の市場はまだ小さく、PDA(電子手帳)への適用が中心でした。しかし、その後タッチパネルの需要は急速に伸び、私たちの開発した技術にも大きな可能性があったことが後に明らかになりました。今日では、タッチパネルはスマートフォンなど多くのデバイスに欠かせない存在となっています。
部門間の連携の大切さ
この経験から学んだのは、研究開発部門と事業部門の間の連携の大切さです。製品開発においては、技術だけでなく市場のニーズや傾向を理解し、それを反映させることが重要です。私たちのプロジェクトは、部門間のコミュニケーション不足が影響して中止に至りましたが、これは学びの一つです。当時の市場が小さかったとはいえ、新しい市場を探るための努力が必要だったのかもしれません。
技術と市場のバランス
技術開発は市場のニーズに合わせて柔軟に進めるべきです。このプロジェクトでは、技術者が市場を深く理解し、営業と連携して製品開発を進めることの大切さが見えてきます。技術革新の成功は技術力だけでなく、市場への適応にも依存しています。当時の私にアドバイスできるなら、もっと積極的に市場にアプローチすることを勧めます。
このプロジェクトからは、研究開発チームにとって貴重な学びがありました。失敗もまた、将来への成功への一歩となり得るのです。この経験は、市場のニーズを敏感に捉え、素早く対応すること、そしてチームワークとコミュニケーションの重要性を教えてくれました。
セミナー/コンサルティングではいかに未来を想像するか、市場を読んで考えるかということを練習します。その上で新規事業のテーマを考えます。興味があればご連絡ください。
革新的な陸上養殖で地域経済を活性化!地方創生の新潮流
ある化学メーカーの新規事業のコンサルティングにて人工海水というものを開発しました。
人工海水とは海水中の塩を含むミネラルの粉です。要は食塩にその他のミネラルが含まれている粉と思ってください。それを水に混ぜ込むと海水が出来上がります。
何に使うかと言うと、陸上養殖です。
陸上養殖は陸の上で海の魚を養殖するので海水が必要となりそのための素になります。
その人工海水を売るためにマーケティング(コンサルティングの一部)をしていたところ、フグやヒラメを飛騨高山で養殖している「飛騨海洋科学研究所」さんと仲良くなりました。
http://hidatorafugu.com/
そこでは、フグを中心に地方(比較的山間部)に養殖のプラントを作って、地域ぐるみで養殖魚のブランド化を進めています。魚種などはお問い合わせください。
また特殊な餌も開発しており、その餌には少しだけ地域の特産物を入れることにしています。
そうすると、地域産の餌で育った地域ブランドの魚が出来上がります。
陸上養殖は海洋養殖と異なり、台風などの影響を受けないため安定した生産が望めます。一方でプラントが必要なので初期の投資がかかります。しかしながらブランド化できれば地域の活性化の効果は大きと考えています。
新規事業創出のコンサルティングでは思わぬ出会いがあり、さらにビジネスが広がっていきます。面白いですね!
ご興味があればご連絡ください。
市場変化と企業内課題: 大企業が直面した技術開発プロジェクト失敗の教訓
新規事業を上手く運営している大企業でさえ、失敗事例は数多く存在します。私が経験したいくつかの事例を、生々しい内容をデフォルメしてお伝えします。
2000年頃、将来大きく成長が期待されていた分野に焦点を当て、自社の得意とする技術を活用した商品開発を進めていました。このプロジェクトは大学からの技術をベースにし、社内で改良を加えた素材を使用していました。全社を挙げた大規模な取り組みであり、比較的大きな研究予算と数十名の研究者が関与していました。多くの困難を乗り越えて試作品が完成し、新聞で大々的に発表されました。これは商品の発売告知ではなく、「このような製品を開発した」という趣旨で、数年後の市場導入を目指し、ニーズを掘り起こすためのマーケティング宣伝でした。
しかし数年後、技術はある程度完成していたものの、この商品にはもはや需要がなく、さらに安価な代替技術が進歩していました。この情報は先に述べた新聞発表の時点で既に明らかでしたが、多くの関係者が関与していたため、プロジェクトをただちに中止することはできず、さらに関係者は認知のバイアス(「ライバルの技術は失敗するだろう」「自社の技術の方が優れている」)に囚われ、ネガティブな情報を上層部に伝えることを避けていました。その結果、莫大な予算を無駄に消費し、顧客の関心が薄れても顧客開拓や技術改良を続けることになりました。
最終的に、経営トップが交代した際に、このプロジェクトはひっそりと中止されました。
この話におけるプロジェクトの失敗原因は主に以下の点に集約されます:
・市場の変化への対応不足: プロジェクトが進行中に該当商品の市場ニーズが変化し、代替技術が進歩したにもかかわらず、これらの変化に対応するための適切な戦略の調整が行われませんでした。
・組織内のコミュニケーション不足: ネガティブな情報が上層部に伝えられなかったため、組織として適切な意思決定ができませんでした。これは、情報の隠蔽や認知のバイアス(自社の技術や製品に対する過度の楽観視)によるもので、結果的に経営層が現実に即した決定を下す機会を失いました。
・リソースの無駄遣い: 大企業の構造と関係者の多さにより、プロジェクトの即時中止が困難であり、結果として無駄な予算と時間が消費されました。これは、組織の柔軟性の欠如と迅速な決定を下す能力の不足を示しています。
・トップマネジメントの方針不在: 経営トップの方針やリーダーシップの不在が、プロジェクトの中止を遅らせた可能性があります。組織のリーダーが明確な方向性を示し、迅速な対応を行うことは、このような状況において非常に重要です。
新規事業の失敗の理由は多岐にわたりますが、これは一つの事例として紹介しました。同様の事例は多数存在すると思いますが、上手くコンサルティングを活用し、方向性を修正していくのが重要です。